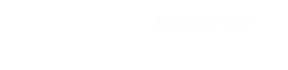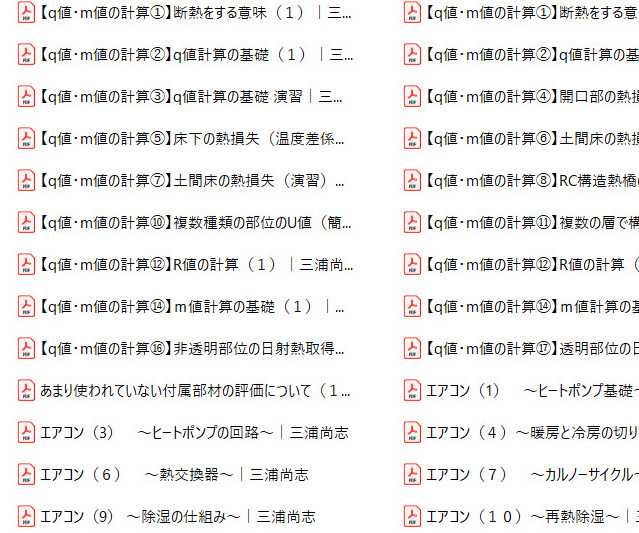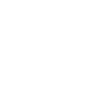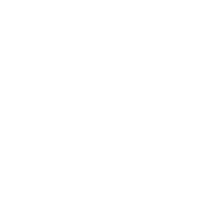社長ブログケヤキの木の下で
建築研究所 三浦尚士さんのnote
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
西日本は梅雨明け宣言が出ましたが
東海地方にはまだ出てません。
とは言いながら、本日も快晴です。
名古屋も岐阜もまだ6月ですが、最高気温は36度の予報。
外仕事の方はご注意ください。
- 先日、新住協の
中部東海支部の総会の話しをしましたが、
このような総会では基調講演や事例発表と
同等以上に大切なのが、同業者同士の情報交換です。
総会の合間の隙間時間や後で開かれる懇親会には、
まだ会ったことの無い会員や
新たに会員になられた方も多くいます。
それに以前から親しくしている人達の中には、
新たに知った事や新たな試みをしている人たちも
多くいますから、
自由に席が移動できて話しができる
懇親会のような時間は絶好の機会となります。
- そんな中で今回ご紹介するのは
建築研究所の 三浦尚志さんのnote
金子建築工業の設計の加藤さんから、
こんなんがありますよと
全てPDFにまとめられていたのを見せてもらいました。
建築研究所というのは日本の建物や工作物すべての
基準や制度などを作っているところで、
建築業界の元締めです。
三浦さんの専門は住宅の暖冷房設備と省エネ設備の評価
その道の専門家の方は専門用語を使うのではなく、
とても分かりやすい言葉で解説してくれます。
一般のこれから家を建てよう
あるいは改修をしようとされる方で、
少しは勉強しておかねばとお考えの方には
うってつけの資料ですし、
実務者の方は当然知っておくべき内容です。
noteの有料箇所は、Xでの拡散で無料になっていますから
リポストすれば全文が読めます。
より多くの方に知っていただきたい内容ですので
皆さんご覧くださいね。
- .
Category
- 家づくりのたいせつな話(527)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(445)
- 温熱環境(212)
- 雑記(252)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(36)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(95)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(31)
- 手仕事 道具 機器(95)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(70)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(29)
- 換気(26)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(69)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)
- 商工会(1)
- 心地よさ(3)
Archive
新住協東海支部総会 土壁の熱容量
- こんばんは紙太材木店の田原です。
昨日は新住協の中部東海支部の総会が恵那でありました。
久保田代表理事の基調講演と、
会員2社の事例発表でした。
(株)ミノワさんと
(有)洞田建設さん
その後、現在恵那市で金子建築工業が建築している
非住宅の木KEYPlusの現場見学。
構造設計は福山弘さん、
前先生の研究室や新住協の前代表の鎌田先生など、
いろんな先生方が絡んだ建物です。
- 先日土壁づくりのワークショップが開催され、
数十人が泥だらけになりながら
壁に泥団子を投げつけていたとか。
土壁の厚みは
最終的には30センチほどになる予定。
将に蔵の壁です。
なぜ土壁があるかと言うと熱を蓄えるため。
どういう効果があるかと言うと
夏、室内に入ってきた熱を
この土壁が取り込むことによって、
室温の上昇を緩やかにできます。
一時的に土壁が熱を吸収するので、
吸収された分の熱は
本来室温を上げることに使われる分、
それが土壁に行くので
室温の上昇が穏やかになるということです。
難しい言葉で言うと
土壁は「熱容量の大きな素材」と言います。
冬、昼間の日射の熱を土壁に蓄えておくと
夜間、土壁が緩やかにその日射の熱を放出してくれます。
- 土壁のように熱容量の大きな素材があると、
室温の変化の差が穏やかになるんですね。
室温が急激に下がったり上がったりではなく、
それが穏やかになります。
この建物では冬に日射の当たる壁が
土壁になっています。
住宅でも掃出しサッシの室内側が
土間コンクリートになってる場合などは、
熱容量を意識した設計と言えます。 - 建物の完成は年末になりそうですが
見学会も予定されていますから、
実務者の方や一般の方も - 興味があれば見学してみてください。
福山さんの木の構造も
隈さんに負けない美しさがありますし、
鎌田先生と前研究室が絡んだ建物は
そんなにあるわけではありません。
実務者必見の建物と言っていいでしょう。
- .
Category
- 家づくりのたいせつな話(527)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(445)
- 温熱環境(212)
- 雑記(252)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(36)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(95)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(31)
- 手仕事 道具 機器(95)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(70)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(29)
- 換気(26)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(69)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)
- 商工会(1)
- 心地よさ(3)
Archive
温度と湿度は別々にはできない
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
昨日は中電が来て、会長農園の銀杏の木の枝打ちでした。
電柱が敷地に入り込んでいるので、
電線近くの枝を取り除く作業です。
高所作業車3台に
収集車2台
総勢13人
主に銀杏の木が対象でしたが、
既に実をつけているのでなんだか残念。
- 通常は電線から3m範囲の枝を伐採しますが
それは中電の都合。
電線より先に木がありますから、
最小範囲での伐採をお願いしています。
なので、3.4年するとまた来られます。 - さて、この季節の風物詩と言えば土間の結露
- 北事務所の土間の床はコンクリート。
床と壁の取り合いを入り隅と言いますが、
このような角は空気が滞留しやすく結露します。
事務所の外の温室計は23.5度 95%
この空気は1度下がれば結露します。
事務所は土足で出入り出来てほぼ外ですから、
コンクリートの床が結露するのは
ごく自然なことです。
この梅雨時の悩みは,湿度が高くジメジメしていること。
エアコンで冷房すれば
ジメジメ感は無くなりますが、
少し肌寒くなってしまいます。
切ればジメジメ感はすぐに戻ってきます… - 対策としては、
再熱除湿のエアコンと言う手もあります。
一昔前の再熱除湿エアコンは、
冷房した空気を再度暖める過程での
エネルギー消費が大きいという認識ですが
最近の再熱除湿エアコンは、
冷房時の排熱を利用したタイプで
以前より、エネルギー消費は少なくて済みます。
この時期だけでなく夏真っ盛りの時期でも、
エアコンの冷房は気温が下がり過ぎて、 - 不快と感じる方にはお勧めのエアコンです。
もちろん冷房時よりは電気代がかかりますが
以前ほどではありませんし、
ずっとそのまま使い続けるのではなく
不快に感じる時間帯で
使い分ければいいのではないでしょうか。
- 新たに購入してまでと言う方も
おられると思いますが、
そんな方にお勧めなのが日射の利用。
梅雨時は使えませんが
夏でしたら2階の窓の日射遮蔽をしないで、
敢えて日射を入れる手法です。
エアコンで冷房して
気温と湿度を下げる
下がり過ぎた気温を
日射を入れることで上げる
これだと湿度だけが下がることになりますし、
余分にお金がかかるわけではありません。
なので、敢えて西と東に窓を設けておきます。 - 日本の梅雨時から夏を快適に過ごすには、
エアコンだけで十分と言うには
実は非常に厳しい気候です。
住宅の性能が向上すればするほど、
夏住まいには設計者の更なる工夫が求められます。 - 上記の解説です。
- 一昔前の家は断熱性も気密性も、
現在の住宅よりもかなり低いレベルでした。
冷房してもどんどん壁や天井、サッシから
熱が入ってきますから、エアコンはフル稼働できました。
つまり、気温を下げることと
除湿がフルにできる家でした。 - 現在の家は断熱性も気密性も
一昔前の家に比べれば遥かに向上してます。 - そうなるとエアコンで冷房すると、
あっという間に気温が低くなり設定温度に達します。 - エアコンは私の仕事は完了したとして
送風モードに切り替わります。 - これをサーモオフと言いますが、
換気をしているので湿気はその間もどんどん入ってきます。
サーモオフするならと
設定温度をさらに下げれば、今度は寒くなります。 - 住宅の断熱性の向上により
室温はコントロール出来るようになりました。 - しかし、湿度コントロールは以前より遥かに難しくなりました。
- エアコンは冷房時には、温度と湿度を
同時にしか処理できないのですから。
- .
Category
- 家づくりのたいせつな話(527)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(445)
- 温熱環境(212)
- 雑記(252)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(36)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(95)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(31)
- 手仕事 道具 機器(95)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(70)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(29)
- 換気(26)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(69)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)
- 商工会(1)
- 心地よさ(3)
Archive
完成見学会のお知らせ
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
すっかり梅雨空に戻ってしまいました。
今週はずっとこんな感じでしょうか。
そうなる前にと、昨日は竹林と土場の草刈り。
3週間前に竹林の草刈りの時の漆にかぶれましたが、
先日ようやく全快。
少しだけ痕が残ってますがそのうち無くなるでしょう。
今回改めて探してみると、疑わしい木がありました。
実際、漆かぶれになる木は何種類かありますから
全部は覚えられません。
今回のはおそらく、ヌルデと呼ばれる木です。
場所を確認しましたから、次回は完全武装で切り倒します。
- さて、本日は中恵土の家の完成見学会のお知らせです。
先行してのお知らせですので、
まだHPには載っていません。
近々、HPに掲載予定ですので
興味のある方はご確認ください。
- 中恵土の家の完成見学会
日時:7月26日(土)27日(日)
各日とも開催時間は10時~16時です。
基本的な性能、仕様は
耐震等級3(許容応力度計算)
Ua値 0.31w/m2K(付加断熱)
C値 既設建物平均0.3cm2/m2
暖房期の自然温度差 11.8度
冷房期の自然温度差 9度
1次エネルギー削減率41%(再エネなし)
1次エネルギー削減率68%(再エネあり)
太陽光パネル 5.16Kw
GX志向型住宅対象
ぎふの木で家づくり支援事業対象
構造材:98%岐阜県産材(桧)
長期優良住宅
設計住宅性能評価
建設住宅性能評価
BELS
- 今後岐阜県では、人口の減少が予測されています。
2020年 197万人
今から25年後の
2050年 137万人
岐阜県の人口は、毎年2万人ずつ減少して
いくことになります。
今後住宅が大量に余ることが分かっている中で、
どんな性能の家も建てるのも自由ですが
これから建てられる家は
お子さんや次の世代が
大規模な耐震改修や断熱改修することなく
容易に住み継がれる家であるべきと考えます。
今回の中恵土の家はそのスタンダードとなりうる家です。
興味のある方のお越しをお待ちしています。
- .
Category
- 家づくりのたいせつな話(527)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(445)
- 温熱環境(212)
- 雑記(252)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(36)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(95)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(31)
- 手仕事 道具 機器(95)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(70)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(29)
- 換気(26)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(69)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)
- 商工会(1)
- 心地よさ(3)
Archive
暑い夏はドアを開けたまま
- おはようございます、
紙太材木店の田原です。
昨夜は暑くて、夜中に目が覚めてしまいました。
梅雨の時期なのに日中も暑く既に真夏の様相ですから、
エアコンの使い方も - 夏バージョンにする必要がありそうです。
- 以前から推奨しているのが、
- ドアを開けたままエアコン。
特に換気が不十分なひと世代前の住まいでは、
一石二鳥の効果を発揮します。
残念ながら最近建てた家でも
換気が絵に描いた餅状態の家では、
十分通用しますからお試しください。
- ドアを開けたままエアコンはその名の通り、
寝室のドアを開けて
エアコンをつけたままにして寝ることです。
換気が絵に描いた餅の家では、
ドアを閉めたままだと寝室の二酸化炭素濃度が
1000ppmを越えるのは普通。
2000ppm
3000ppmにもなります。
ドアを開けたままにするとそれを防ぐことができます。
次に、ドアを閉めてエアコンをつけると
寒くなりすぎる傾向にあります。
温度設定を色々変えても、
朝まで安眠となるケースはそれほど多くありません。
寒さで目が覚めたり、
夏なのに毛布を掛けたりとなります。
タイマーをかけて寝る場合、
エアコンが止まれば
暑さが戻って目が覚める
もう一度タイマーをかける
そんなことを繰り返すことになります。
- エアコンは確かに優れモノなんですが、
特に冷房をしようとする場合、
狭く閉じられた空間で臨機応変に働くのは苦手です。
簡単に言うと6畳とか8畳の
一部屋の閉じられた空間で使うには、
エアコンの冷房能力がありすぎるんですね。
四字熟語に 牛刀割鶏 と言う言葉がありますが、
まさにそれです。
なのでエアコンが働きやすい空間や
場所を作ってあげることが、快適性につながります。
- エアコンにとってその空間が狭すぎるのなら
- 部屋を広くしてあげればいいわけで、
- ドアを開ければそうなります。ドアを全開にするか
半分ほど開けるか
あるいは10センチほど開けるか
温度設定や寝室で寝る人数などで変わりますから、
どれだけ開けるか試行錯誤してみてください。
寝室が寒くなり過ぎず、
CO2濃度も下がりますから一石二鳥です。
- .
Category
- 家づくりのたいせつな話(527)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(445)
- 温熱環境(212)
- 雑記(252)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(36)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(95)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(31)
- 手仕事 道具 機器(95)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(70)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(29)
- 換気(26)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(69)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)
- 商工会(1)
- 心地よさ(3)