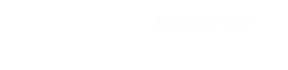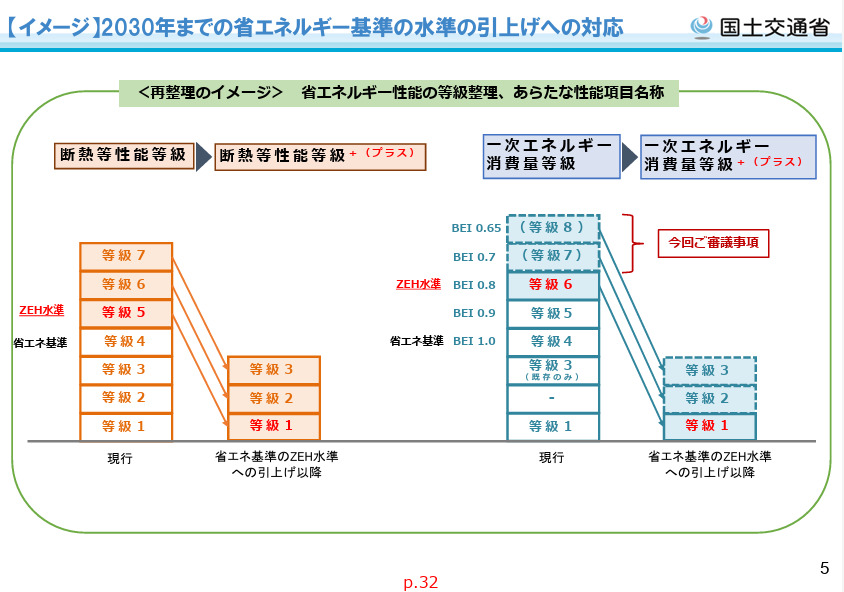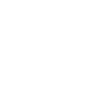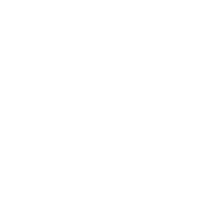社長ブログケヤキの木の下で
地方自治体の住宅補助金
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
今シーズンの筍、大台の100本を越えて
111本の収穫になりました。
そろそろ終盤ですが、あとどれだけ出るか楽しみです。
- さて、本日は補助金のお話し
住宅を建てる時に補助金が出ますが、
国からのものと地方の自治体である県や市のものがあります。
東京都の東京ゼロエミでは
一定水準の性能や設備を満たせば、 - 240万円の助成金がでます。
札幌版次世代住宅の補助金も、
要件を満たせば220万の補助金が出ます。
随分高額ですが、東京や札幌だけでなく
鳥取NE-ST 200万
信州健康ゼロエネ住宅200万
やまがた省エネ健康住宅200.2万
せんだい健幸省エネ住宅310万
etc
補助金の額も性能のランクに応じて上下して、
上記の額は上限です。
国の住宅の補助金との併用は認められませんが、
自治体独自の補助金は併用ができるものもあります。
国のGX志向型住宅の補助金の160万が - 小さく見えてしまいます。
- 他にも探せば色々とありますが、
なぜ国や地方の自治体が
これほど住宅に対して補助金を出すのか?
一昔前は与党の選挙対策であったり、
あるいは景気対策と言った側面もありましたが、
それにしても金額が大きくなっています。
2050年のカーボンニュートラルもありますが、
主な理由は空き家対策だと思われます。
現在多くの家が空き家になっています。
その主な理由が、
耐震性が低い
断熱性が悪い
省エネではない
生活コストが大きい
改修には大きな費用が掛かる
そんな中古住宅には住みたくない訳で
新築住宅になりますが、
その新築住宅の性能が低ければ同じことの繰り返し。
ますます空き家増えていくことになります。
ただでさえ有り余ってる住宅が、
更に増えていく・・・
自治体にとって放置されている空き家は
頭痛のタネでしかありません。
なのでそんな空き家を減らす策の一つが、
誘導策としての高額な補助金となります。
同時に国は基準法を改正し、一定水準以下の住宅を - 建てさせないようにし始めました。
下から法律によって性能を押し上げ
低い性能の家は建てさせないようにして、
上にはアメをぶら下げ引き上げるということになります。
- 実は欧米では、30年も前からしていることです。
ようやく日本も遅すぎるきらいはありますが、
そうなり始めたと見ていいでしょう。
どんな家を建てるのも自分の自由
自分が死んだ後の家なんて
野となれ山となれ
そんなことは知らん
子供が何とかする
そんな時代は、既に遠い昔の話しとなりました。
- さて、岐阜県の住宅補助金
実は国の補助金と併用が可能です。
①ぎふの木で家づくり支援事業32万
②脱炭素社会ぎふモデル住宅事業費補助金40万(昨年)
②の詳細はまだ発表されてませんが、
近日中に県のHPに出されます。
①は国の補助金を貰うと約半額の17.6万になりますが、
GX志向型の160万と合わせると
160+17.2+40
217.2万の補助金になります。
県産材を使うことや省エネなど、
一定基準を満たせば補助対象になります。
岐阜県を含め地方で新築を検討される方は、
自分の家が基準を満たしているか
設計者に確認してみてください。
- .
Category
- 家づくりのたいせつな話(522)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(436)
- 温熱環境(212)
- 雑記(253)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(37)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(97)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(32)
- 手仕事 道具 機器(93)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(74)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(28)
- 換気(25)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(67)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)
Archive
2030年までの省エネ基準
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
雨ですね。
雨後の筍(うごのたけのこ)
今月11日に今シーズンの筍掘りが始まって
昨日までの収穫は91本
昨日スーパーで見かけた京都府産の筍は驚きの価格
- 1本2858円、税込みで3086円・・・
シーズン中は筍が飛び交う田舎で、
誰が買うのか?
筍は掘ったらすぐに茹でるが基本。
いくら京都府産でも
収穫してから2.3日は経ってるわけで、
どんな味がするか気にはなるけど・・・
- 先日開かれた国交省の
社会資本整備審議会建築分科会で
一次エネルギー消費等級の見直しが検討されました。
新たに現行の最高等級6での上に
等級7.等級8を設けるようです。
- それに伴って右の図の一次エネルギー消費量等級は
等級6の上に7と8を設け、
新基準は それを等級1.2.3とするものです。
断熱等性能等級も現行の等級5.6.7を
それぞれ等級1.2.3にするものです。
従来のZEH水準が最低基準になります。
- 断熱性能等級はUa値で決まりますが、
以前からお伝えしてるように
Ua値が良いからと言って必ずしも省エネにはならない
つまり、
冷暖房費やエネルギーの
消費量がUa値と比例してないんですね。
Ua値が良ければ、
必ずしもエネルギー消費も良くなる訳ではありません。
新住協もPHJも、Ua値は基準にしていません。
- 一次エネルギーの消費量には
設計された住宅に住んだ時、
エネルギーがどれだけ必要かで等級分けがしてあって
基準のエネルギーと比較して - BEIと言う数値で出します。
対象は冷暖房、換気、給湯、照明、家電
一次エネルギー消費量等級6はBEIが0.8
つまり、基準の80%のエネルギーで住める家
新たな等級7はBEIが0.7
等級8は0.65
つまり基準の65%のエネルギーで
住める家となります。
2030年までにはこんな基準にしますよ
と言うことです。
一次エネルギー消費等級8はBEIが0.65で
太陽光パネルは含んでいない数値ですから
断熱だけでなく、
日射の利用や遮蔽にも
工夫がほしいところで
設計者は腕の見せ所でしょうか。
もちろん、予算やデザインとの
兼ね合いもありますから
そんなバランス感覚も求められます。
今回の省エネルギー基準の水準の引き上げの検討は
窓を小さくしたり
数を少なくする
安易な上位等級狙いの
封じ込めの意味もありますが
住まいの省エネ性能に対する国としての正常な方向を
示しているとも言えます。
- これからの住まいは
性能的には
耐震性
断熱性
一次エネルギー消費量 で
評価されることになります。 - .
Category
- 家づくりのたいせつな話(522)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(436)
- 温熱環境(212)
- 雑記(253)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(37)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(97)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(32)
- 手仕事 道具 機器(93)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(74)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(28)
- 換気(25)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(67)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)
Archive
決められたプランから選ぶ?
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
- 4月11日から筍が出始め、一昨日は15本、昨日は17本。
今年は出が悪いと近隣では言われてますが、
既に50本以上収穫してます。
今週一杯収穫できそうですから
例年通り100本ほどになりそうです。
- さて、工事中の可児の家C
杉板も張り終わり、順調に工事が進んでいます。
ミニ開発の分譲地で6宅地ありますが、
工事中の可児の家C以外は全て平屋。
70坪(230m2)程度の敷地の広さ、
そこに30坪前後の平屋です。
2台分の駐車場を取ると南側には - それほどスペースはありません。
6宅地の真ん中を南北に進入路が付いていますから、
建物の東側か西側で接道することになります。
つまり南側には、お隣の建物が来ることになります。
平屋であれば南面からの日射取得に難儀しますが、
そもそも南側の家が平屋であることを
差し引いても、
どの家も日射の事なんて
これぽっちも考えていない設計に見受けられます。
- 上の写真は某大手HMの建設中の家ですが、
この2つの窓は西に面しています。
それぞれ4畳半の部屋で窓はここしかありません。
なぜわかるかと言うと、道路向かいの屋根の上から
よく見えるんですね。
窓のサイズは1.6mx0.7mと大きめ。
冬は大丈夫でも、夏はどうするんだろうと
他人事ながら心配になります。
数百もあるプランから、
敷地だけにあったプランをそのまま当てはめて建てるのが
よくわかります。
日射の取得や遮蔽は冷暖房費に直結しますし、
暮らし易さとも関係してきます。
屋根にパネルを載せてるからエアコンで冷やせば大丈夫?
全館空調だから大丈夫?
- 夏の気温35度、湿度60%の時
4.5畳の部屋
西向きの1.6x0.7の窓
何度、何%の空気を1時間にどれだけ送れば、
27度、50%の室内になるか
設計者に計算してもらっていると思いたいですね。
決められたプランからしか
選ぶことができないというのはHMの都合ですが、
予算的な制約があるとなると住まい手の都合とも言えます。
どう考えるかは住まい手次第ですから
慎重にお考え下さい。
- .
Category
- 家づくりのたいせつな話(522)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(436)
- 温熱環境(212)
- 雑記(253)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(37)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(97)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(32)
- 手仕事 道具 機器(93)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(74)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(28)
- 換気(25)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(67)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)
Archive
高性能な賃貸住宅も選択肢の一つ
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
先日、黒部市にある YKKのパッシブタウンに - 行ってきました。
建物は既に第5街区まで完成していて、
第5街区の外構工事中でした。
夏頃にその外構工事も完成するそうで、
一般公開はその後のようです。
- 第3街区は 森みわさんの設計で改修物件です。
YKKの社宅だった建物。
昔の4階建て程度の公団のアパートを
思い出していただくと、想像できるかもしれません。
コンクリートで造られた建物ですから、
断熱の改修は外側から断熱材を貼り付ける手法です。
壁にはEPSというポリスチレンの断熱材を
厚さ15センチで貼り付けてあります。
壁がコンクリートのような
熱容量の大きな素材でできた建物は
室内側ではなく、壁の外側に断熱材を
取付けるのが基本。
ドイツでも同様な断熱改修が行われています。
この外側に断熱材を貼り付けて
断熱改修する時に、
邪魔になるのがコンクリートでできた
躯体一体型のバルコニー。
バルコニーを外側から断熱材で
包んでしまうことはできません。
そうなるとバルコニーは熱橋と言って
熱が逃げていく通り道になるんですね。
この建物も改修前にはバルコニーがありましたが、
熱橋対策で撤去。
写真を見るとバルコニーがついてますが、
これは後付けのバルコニーで
躯体一体型ではありません。
- 性能レベルは2棟のうち、
J棟はパッシブハウス認定
K棟はアメリカのLEED for Homes認定でから
性能的には折り紙付きです。
日本でも今後このような
高性能な集合住宅が増えていくと思われます。
既設の建物を改修すれば、
既存のコンクリートの建物を撤去して
新設するよりも、安価にできます。
- 話しは変わりますが
高性能賃貸研究会と言うのがあります。
新住協の夢建築工房の岸野さんや
東大の前先生も関わってますが、
時代が高性能な賃貸住宅を
求めていると言っていいでしょうか。
上記のパッシブタウンも実は賃貸住宅。
検索していただくと、家賃も出ています。
建築費が高騰していて
都心の新築マンションは1億を越えています。
住宅価格も同様に高騰してますし、
職人不足の問題もあります。
ひと世代前は新たに土地を購入して
新築住宅を建てることは普通であり
一般的でしたが、
これからの時代はどうでしょう?
そもそも夫婦二人の実家は
どうなるか?
どうするか?
誰かが何とかしてくれるか?
更に先を考えると、
仮に家を建てたとして
その家はお子さんの
資産になるか
負債になるか
- 現在の空き家の多くは
耐震不足、断熱不足が主な原因ですが、
建てた家が十分それらを満たしているかどうか
満たしていなければ
負債になる可能性が高いと思っていいでしょう。 - これから新築を検討される方は
- 幾つもの選択肢がありますが、
- 同時に検討すべき項目も数多くあります。
- 親世代の時の様に何も考えず、
土地を買って家を建てる時代は終わりました。 - 耐震性、断熱性、省エネ性
実家の終活、ローン金利
資材の高騰、インフレ
子供達への相続 etc. - 家づくりは慎重に進める必要があります。
- .
Category
- 家づくりのたいせつな話(522)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(436)
- 温熱環境(212)
- 雑記(253)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(37)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(97)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(32)
- 手仕事 道具 機器(93)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(74)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(28)
- 換気(25)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(67)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)
Archive
南面のサッシガラスと暖房費
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
昨日から富山に来てます。
途中のひるがの高原は吹雪で、車載温度計の外気温は0度
- 幸い、路面に積雪はありませんでしたから
安全に来ることが出来ました。
積もるような雪だったら、サービスエリアで足止めでした。
- 富山に来たのはYKKの黒部萩生製造所PSスタジオと
パッシブタウン
それに、黒部製造所の見学です。
紙太材木店では標準的なサッシは
エクセルシャノンとYKKです。
APW430やNS50を使っていますが、
サッシも年々進化しています。
特にサッシに使われるガラスについては、
サンゴバンの優れたガラスが使われるようになりました。
木製サッシでは佐藤の窓のスマートウィンや
シャノンのNS50でも使われていますし、
YKKでも同様です。
- サッシのガラスの種類と聞くと
ペアガラスやトリプルガラスが思い出されますが、
実は住宅で使われるサッシのガラスは - 何十種類もあります。
QPEXやホームズ君などの計算ソフトで、
選択できるガラスのリストを見ると多くの方は驚かれます。
主に、
Ug値と言われるガラスの熱還流率と
日射取得率のηg値で分けられます。
Ug値は熱還流率なんて言うと分かり難いですが、 - 断熱性の事です。
- 最近はUa値で住まいの断熱性を数値化しますし、
サッシから逃げていく暖房エネルギーは
壁よりも多いと言うところが強調され、
Ua値をよくするためサッシを小さくしたり、
出来るだけサッシの数を少なくする
設計者やHMもあります。
新住協でもPHJでも日射取得による
暖房エネルギーの削減効果を見ています。
なので、簡単に言うと
南面のサッシは出来るだけ大きく
出来るだけ多くと言うところを意識しています。
- そこで関係してくるのがサッシのガラスの
Ug値(熱貫流率=断熱性)と
ηg値(日射取得率)
今までの日本のサッシのガラスは
Ug値(熱貫流率=断熱性)が良ければ
ηg値(日射取得率)が悪い
ηg値(日射取得率)が良ければ
Ug値(熱貫流率=断熱性)が悪い
二つの値は相反する関係にあったんですね。
しかしサンゴバンのガラスは
二つが両立してるガラスです。
この二つが両立すると
南面にこのガラスを使うことで、
暖房エネルギーを大きく削減することができます。
日射を取得するタイプのガラスと - 取得しないタイプのガラスのηg値は0.6前後と0.3前後で、
- 約2倍の違いがあります。
- 現在建設中の可児の家で
- どれくらい暖房費が違ってくるか計算すると、
- ガラス取得しないタイプに変えただけで
- 暖房費は約30%アップ自然温度差は2度低下します。
- でも逆に取得しないタイプは断熱性が少し上がるので、
- Ua値が0.01良くなります。
- Ua値がいくら良くなっても、暖房費が上がるようでは意味がありません。
サッシは、どんなガラスを使うかによって
暖房費は大きく異なります。
デザインや性能、予算のバランスを見て
設計者と相談しながらお決めください。
- .
Category
- 家づくりのたいせつな話(522)
- 雨漏れ(25)
- 高性能 省エネ(436)
- 温熱環境(212)
- 雑記(253)
- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)
- 室内環境(37)
- MOKスクール(28)
- 紙太材木店の考え(97)
- 建築巡礼(36)
- レイモンド(3)
- 耐震のこと(32)
- 手仕事 道具 機器(93)
- 断熱のこと(92)
- イメージ 仕上がり(74)
- 暮らし(181)
- 古い民家の再生(80)
- 経年変化(7)
- イベント情報(28)
- 換気(25)
- 結露(29)
- インテリア(20)
- メンテナンス(7)
- 紙太材木店の仕事(2)
- 素材(67)
- サッシの性能(51)
- 料理(141)
- 室内環境と健康(15)
- 庭造り(4)
- リフォーム(55)
- 現場レポート(184)
- 性能とデザインのバランス(17)
- 耐久性(3)
- 住宅医 ぎふ木造塾(22)
- 造作家具(25)
- 本の紹介(40)
- ZEH(3)
- 百年の家プロジェクト(45)
- 薪ストーブ(48)